
「訪問介護の人手不足が深刻で、外国人材の採用を本格的に検討したいけれど、制度が複雑で何から手をつければ良いかわからない」人手不足に悩む訪問介護事業所の経営者や人事担当者にとって、2025年4月から解禁された外国人材の受け入れは、大きな関心事ではないでしょうか?
ただし、事業者には質の高いサービスを提供し、外国人材が安心して働ける環境を整えるための、運用ルールが定められています。ルールを正しく理解せず採用を進めてしまうと、思わぬトラブルや法令違反につながるリスクもあるでしょう。
そこで今回は、外国人材の訪問介護が解禁された背景や対象となる在留資格、事業者や人材に求められる要件など、採用担当者が知っておくべき情報を解説します。制度を正しく理解し、自社の新たな戦力となる外国人材を安心して受け入れるための第一歩として、ぜひご活用ください。
目次
外国人材に訪問介護が解禁される背景
急速な高齢化を背景に、訪問介護の需要は年々高まっています。しかし、高まる需要に反して介護現場では深刻な人手不足が続いており、サービスの安定供給が課題となっています。
こうした状況を打開するため、これまで認められていなかった外国人材による訪問介護が解禁されました。ここでは、外国人材に訪問介護が解禁される背景について詳しく解説します。
訪問介護の受給者数が年々増加している
訪問介護の需要は高齢化により拡大し続けています。特に、食事や入浴、排泄などの介助を直接行う「身体介護」を中心に、サービスの受給者数は増加傾向にあります。
実際に厚生労働省のデータによると、受給者総数は平成19年度の約100万人から令和3年度(2021年度)には約140万人にまで達しました。
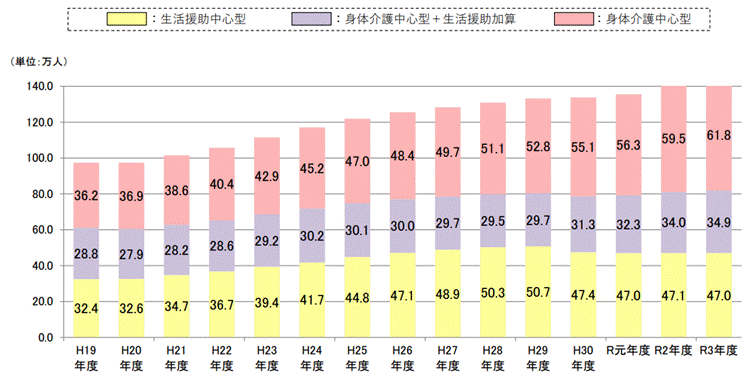
画像引用元:訪問介護(厚生労働省)
この背景には、要介護度の高い高齢者が増えていることがあります。要介護度が高くなるほど、調理や掃除などの生活援助に加えて、身体介護の必要性が高まる傾向にあるからです。
このように、より専門的なケアを必要とする利用者が増え続けていることが、訪問介護サービスの需要を押し上げる大きな要因となっています。
訪問介護員の人手不足が続いている
サービスの需要が増え続ける一方で、担い手である訪問介護員の不足は深刻な状況です。厚生労働省の調査では、約8割もの訪問介護事業所が「従業員が不足している」と感じていると回答しています。
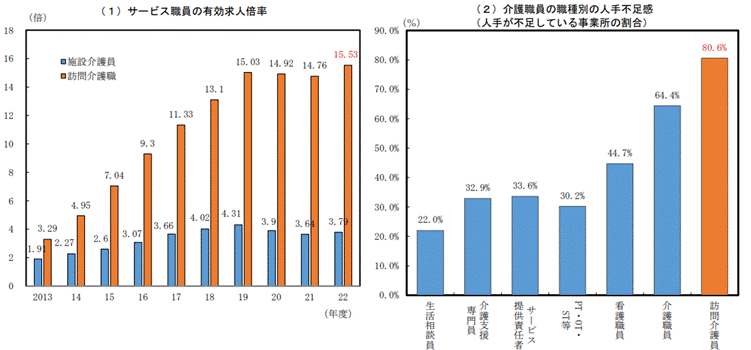
画像引用元:訪問介護(厚生労働省)
また、グラフを見てもわかるとおり、2022年度の訪問介護職の有効求人倍率は15.53倍に達し、施設介護員の3.79倍と比較して約4倍も高い数値を示しています。その結果、多くの事業所が、人手不足を理由に新規のサービス依頼を断らざるを得ないケースも発生しており、事業の継続すら危ぶまれる事態となっています。
訪問介護員の離職率が低い
深刻な人手不足が続く訪問介護業界ですが、意外にも離職率は他の介護サービスと比較して特別高いわけではありません。公益財団法人介護労働安定センターが公表した「令和5年度介護労働実態調査」では、介護職員の離職率が13.6%だったのに対し、訪問介護員の離職率は11.8%でした。
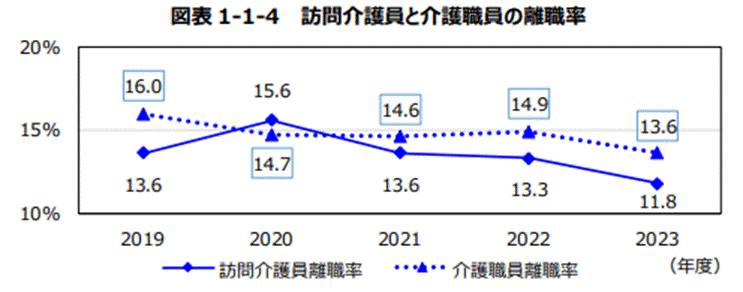
画像引用元:令和5年度「介護労働実態調査」結果の概要について(公益財団法人介護労働安定センター)
それでも人手不足が解消されないのは、そもそも訪問介護の仕事を選ぶ新規入職者が少ないという構造的な課題があります。つまり、「辞める人が多い」のではなく「入ってくる人が少ない」ことが人手不足の根本的な原因といえるでしょう。
訪問介護に従事できる外国人材の在留資格
外国人材が訪問介護サービスに従事するには、国が定めた在留資格が必要です。これまでは高い専門性を持つ人材に限られていましたが、深刻な人手不足を受け、2025年4月から「技能実習」や「特定技能」でも訪問介護が可能になりました。ここでは、訪問介護に従事できる4つの在留資格の特徴について解説します。
- 在留資格「介護」
- EPA(経済連携協定)介護福祉士(候補者)
- 技能実習「介護」
- 特定技能1号「介護」
参照元:外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について(厚生労働省)
在留資格「介護」
在留資格「介護」は、介護分野で最も専門性の高い国家資格を持つ人材に与えられる在留資格です。取得のハードルは高いですが、その分、即戦力として大きな期待が持てます。
■在留資格「介護」の主な特徴
- 介護福祉士国家試験に合格した者のみが対象
- 高い日本語能力(原則N2相当)が必要になる
- 訪問介護サービスを含むすべての介護分野で就労できる
- 就労期間の制限なし(更新可能)
高い専門性を保有しているため、事業所の中核を担う人材として長期的に活躍してもらうことも可能です。
EPA(経済連携協定)介護福祉士(候補者)
EPA(経済連携協定)とは、二国間の経済的な結びつきを強める協定のことで、この枠組みを利用して介護人材を受け入れる制度が「EPA介護福祉士(候補者)」です。将来の専門職候補として、計画的に人材を育成できることが特徴です。
■EPA介護福祉士(候補者)の主な特徴
- インドネシア、フィリピン、ベトナムなど協定締約国から受け入れを行う
- EPA介護福祉士候補者からEPA介護福祉士に移行すれば訪問介護に従事できる
- 国家試験合格後に在留資格「介護」へ変更できる
実務を通して、日本の介護を学びながら国家資格取得を目指す育成型の制度です。合格後は質の高いサービスを提供してくれる貴重な人材として、長期的な活躍が期待できるでしょう。
技能実習「介護」
技能実習「介護」は、日本の進んだ介護技術を開発途上国へ移転し、母国の経済発展に貢献することを目的とした在留資格です。これまで対象は施設介護に限られていましたが、法改正により訪問介護現場でも可能になりました。
■技能実習「介護」の主な特徴
- 発展途上国への技能移転を目的としている
- 基礎的な日本語対応力があれば取得できる
- 一部条件下で訪問介護が可能となった
あくまで期間限定での就労となりますが、一定の研修を受け、日本語能力も有しているため、訪問介護現場の即戦力として人手不足を解消する重要な役割が期待されています。
特定技能1号「介護」
特定技能1号「介護」は、深刻な人手不足に対応するため、即戦力となる外国人材を迅速に受け入れることを目的とした在留資格です。技能実習と同様に、2025年4月から一定の要件下で訪問介護サービスへの従事が可能となりました。
■特定技能1号「介護」の主な特徴
- 2025年4月より訪問介護への従事が認められるようになった
- 「介護職員初任者研修」などの研修修了、日本語能力試験(JLPT)N4以上が必要になる
- 最長5年、日本で就労できる(一部人数制限あり)
- 国家試験合格後に在留資格「介護」へ変更できる
技能実習からの移行や試験合格によって資格が得られるため、比較的スムーズに人材を受け入れられます。そのため、急な人員不足に迅速に対応しやすい点がメリットと言えるでしょう。
訪問介護に従事可能な外国人材を受け入れられる施設・サービス
外国人材による訪問介護は、すべての施設やサービスで認められているわけではありません。制度上、受け入れ可能な事業所の形態や、従事できるサービスの種類には明確なルールが定められています。
受け入れを検討する際は、まず自社がその対象となるかを確認することが重要です。ここでは、どのような施設やサービスで外国人材が活躍できるのか解説します。
参照元:外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について(厚生労働省)
受け入れ対象となる介護施設
外国人材を訪問介護に従事させる場合、雇用主となれるのは原則として「訪問介護事業所」です。また、施設の種類によって受け入れの形態が異なります。
| 受け入れが可能な事業所の形態 | 概要 |
|---|---|
| 訪問介護事業所 | 一般的な訪問介護サービスを提供する事業所(直接外国人材を雇用する場合) |
| 訪問介護事業所を併設する施設 | ・サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) ・住宅型有料老人ホーム など |
これまで特定技能外国人材などの雇用が認められていなかったサ高住などでも、施設に訪問介護事業所が併設されていれば、事業所が雇用主となって外国人材を受け入れられます。ただし、その場合であってもサ高住や住宅型有料老人ホームの施設職員ではなく、訪問介護職員として業務に従事する必要があります。
参照元:対象施設(厚生労働省)
受け入れ対象の訪問系サービス
外国人材が従事できるのは、一般的な「訪問介護」だけではありません。今回の制度改正により、介護保険法などに基づく、以下のような訪問系サービスが対象となりました。
| 外国人材が従事できる主な訪問系サービス | 概要 |
|---|---|
| 訪問介護 | 利用者の自宅で身体介護(食事、入浴、排泄の介助など)や生活援助(調理、掃除など)を提供できる |
| 訪問入浴介護 | 専用の浴槽を積んだ訪問入浴車などで利用者の自宅を訪問し、入浴の介助を行う |
| 介護予防訪問入浴介護 | 要支援者を対象に、簡易浴槽を用いて自宅で入浴の介助を行い、心身機能の維持や自立支援を行う |
| 夜間対応型訪問介護 | 夜間帯に定期的な巡回訪問を行うほか、利用者からの通報に応じて随時訪問し、介助や安否確認を行う |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 介護職員や看護師などが連携し、定期的な訪問と随時対応する |
| 総合事業における訪問型サービス | 市町村が主体となって実施する、要支援者などを対象とした訪問サービスを行う |
このように、幅広いサービスで外国人材の受け入れが可能になったため、事業所はそれぞれの実情に合わせて人材を配置し、人手不足の解消を図れます。
外国人材が訪問介護に従事できる要件
外国人材が訪問介護に従事するには、国が定めた要件を満たす必要があります。なぜなら、利用者と1対1で接するサービスの質と安全性を担保するためです。ここでは、外国人材が訪問介護の担い手となるためにクリアすべき3つの要件を解説します。
- 介護分野の在留資格を保有していること
- 介護職員初任者研修課程などを修了していること
- 介護事業所等での実務経験があること
参照元:外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について(厚生労働省)
介護分野の在留資格を保有していること
外国人材が訪問介護で働くための最も基本的な要件は、国が認めた介護分野の在留資格を保有していることです。
■訪問介護に従事できる主な在留資格
- 在留資格「介護」:介護福祉士の国家資格が必要な、最も専門性の高い資格です。
- EPA(経済連携協定)介護福祉士:インドネシア、フィリピン、ベトナムから介護福祉士候補者を受け入れ、介護福祉士を育成する制度です。
- 技能実習「介護」:日本の技術を母国へ移転することを目的とした制度です。
- 特定技能1号「介護」:介護分野の人手不足に対応するため、即戦力となる人材を受け入れる制度です。
これらの在留資格は、それぞれ取得方法、在留できる期間、求められる日本語能力などが異なります。そのため、事業所は受け入れたい外国人材がどの資格に該当し、どのような要件を満たしているのかを正確に把握しておく必要があるでしょう。
介護職員初任者研修課程などを修了していること
介護の基本的な知識と技術を証明する公的な研修を修了していることも、訪問介護に従事するための必須要件です。
■修了が必要な主な研修
- 介護職員初任者研修:介護職として働く上で基本となる知識・技術を習得する研修
- 生活援助従事者研修:調理や掃除といった生活援助を中心に、サービス提供の基本を学ぶ研修
これらの研修では、介護の理念や基本的な身体介護の方法、緊急時の対応などを体系的に学びます。そのため、研修を修了していることが、一定水準のスキルがあることの公的な証明となります。
介護事業所等での実務経験があること
訪問介護に従事する外国人材には、サービスの質と安全性を担保するため、一定の実務経験が求められます。
■実務経験に関する要件
- 原則:介護施設などで1年以上の実務経験があることが求められる
- 例外:実務経験が1年に満たない場合でも、以下の条件を満たすことで、例外的に従事が認められる
- 日本語能力試験(JLPT)N2相当など、在留資格で求められる基準以上の語学力がある
- 事業所が通常より長期間の同行訪問を行うなど、特別なOJT(実地研修)計画を立てて実施している
基本的には即戦力として期待できる実務経験が重視されますが、本人の能力や事業所のサポート体制が整っていれば、柔軟な対応も可能となっています。
解禁される訪問介護の改正内容
外国人材による訪問介護の解禁にあたり、国はサービスの質を担保し、外国人材が安心して働ける環境を整えるためのルールを定めました。受け入れ事業者には、ルールを遵守し、適切な受け入れ体制を構築することが義務付けられています。ここでは、事業者に求められる5つの改正内容を詳しく解説します。
- 外国人介護人材への研修実施
- 同行訪問等によるOJTの実施
- 外国人介護人材の意向確認、キャリアパスの構築等
参照元:外国人介護人材の訪問系サービス従事における留意点について(厚生省)
外国人介護人材への研修実施
外国人材が訪問介護に従事するにあたり、受け入れ事業者には質の高い事前研修の実施が義務付けられています。訪問介護は利用者の自宅というプライベートな空間で、介護者と利用者が1対1で接するため、施設介護以上に高度なコミュニケーション能力と個別対応が求められるからです。
事業者が実施すべき研修には、主に次の内容が含まれます。
- 訪問介護の基本事項:訪問系サービスの基本理念や業務手順
- 生活支援技術:利用者の自宅で行う身体介護や生活援助の具体的な技術
- コミュニケーションスキル:利用者や家族と信頼関係を築くための傾聴、受容、共感の技術
- 日本の生活様式:利用者の生活文化を尊重し、適切に対応するための知識
- 緊急時の対応:不測の事態が発生した際の具体的な対応方法や連絡体制の確認
研修を通じて、外国人材が万が一の事態にも冷静に対処できる知識と技術を身につけ、質の高いサービスを提供できるようにすることが求められています。
同行訪問等によるOJTの実施
座学での研修だけでは、現場での様々な状況に対応することは難しいです。そのため、外国人材が一人で訪問サービスを提供できるようになるまで、サービス提供責任者や経験豊富な先輩職員が同行し、実地で指導を行うOJTが義務付けられています。
同行訪問のOJTの進め方は、次のとおりです。
- 初期は見学中心に行う
- 指導のもとで部分的に業務を行う
- 最終的には本人中心で業務を行う
段階的な研修を通して、外国人材は自信を持って業務に取り組めるようになり、訪問サービスの品質向上にもつながるでしょう。
外国人介護人材の意向確認、キャリアパスの構築等
外国人材に長く活躍してもらうためには、働きがいと将来のプランを示すことが重要です。そのため、受け入れ事業者には、本人と密にコミュニケーションを取り、個々に合わせたキャリアパスを提示することが求められています。
キャリアパスの提示方法は、次のとおりです。
- 外国人材本人の意向を確認する:従事してもらう業務内容や注意点を丁寧に説明し、本人の希望や考えを確認する。
- 目標を共有する:将来どのような介護職員になりたいか、どんなスキルを習得したいかなどキャリアの目標を本人と共有する。
- キャリアアップの計画を共同で作成する:共有した目標に基づき、具体的な「キャリアアップ計画」を本人と一緒に作成する計画には、以下のような支援を盛り込むことが求められる。
- 介護福祉士などの資格取得に向けた支援
- より高度な日本語能力を身につけるための学習支援
- その他、本人の希望に応じた研修参加の機会提供など
個々の目標に寄り添った計画を立て、事業者としてその実現を継続的にサポートしていくことが義務付けられています。
ハラスメント対策
訪問介護は、利用者の自宅という密室空間でサービスを提供するため、利用者やその家族からのハラスメント行為が外部から見えづらいといえます。特に、文化や言語の壁がある外国人材は、被害に遭うリスクも懸念されています。
受け入れ事業者には、外国人材をハラスメントから守るための具体的な対策を講じることが義務付けられました。
■事業者に義務付けられるハラスメント対策
- ハラスメント防止マニュアル作成・共有する
- 管理者の役割明確化と対応ルールを周知する
- 相談窓口を設置する
対策を確実に実施し、外国人材が安心して働ける職場環境を整えることが求められます。
ICTの活用等による環境整備
不測の事態が発生した際の安全確保と、日々の業務負担を軽減するために、ICT(情報通信技術)の活用を含めた環境整備が事業者に義務付けられています。たとえば、次のような環境整備が必要になります。
- 緊急時マニュアルの整備・駆けつけ体制を構築する
- サービス記録や申し送りの情報共有システムを導入する
- コミュニケーションアプリや多言語翻訳機を活用する
- 見守りカメラ・記録ソフトによる効率化を図る
ICTは緊急時の対応だけではなく、記録の簡素化・業務効率化の検証にも有効とされ、外国人介護人材の安心と定着につながるでしょう。
外国人材への訪問介護解禁の運用ルール
外国人材による訪問介護サービスの質と安全性を確保するため、国は詳細な運用ルールを定めています。ここでは、事業者が把握しておくべき運用ルールを4つの側面から解説します。
参照元:外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について(厚生労働省)
受入れ事業所が遵守すべき事項
外国人材を受け入れる事業所には、サービスの質と人材の保護を目的とした、次の5つの遵守事項が義務付けられています。
- 研修の実施
- 一定期間の同行訪問等必要なOJTの実施
- 外国人介護人材への丁寧な説明・意向確認、キャリアアップ計画の策定
- ハラスメント対策の実施
- 現場で不測の事態に備えたICTの活用を含めた環境整備
研修の実施
事業者は、外国人材が日本の介護現場で適切に業務を遂行できるように、質の高い事前研修を実施する義務があります。研修では、主に次の内容を含める必要があります。
- 訪問介護の基本技術や知識
- 日本の生活様式や文化
- 利用者とのコミュニケーションを図るためのスキル
- 緊急時を想定した対応訓練
質の高いサービスを提供するために、訪問介護の土台を築くための重要な研修です。
一定期間の同行訪問等必要なOJTの実施
座学研修で得た知識を実践で活かすため、事業者はOJT(実地研修)として、一定期間の同行訪問を行う必要があります。経験豊富なサービス提供責任者や先輩職員が一緒に利用者の自宅を訪問し、現場でしか学べないケアの方法や状況判断を直接指導します。
OJTを通じて、外国人材は一人ひとりの利用者に合わせた適切なサービスを提供する能力を養い、一人で業務を遂行できる自信がつきます。
外国人介護人材への丁寧な説明・意向確認、キャリアアップ計画の策定
外国人材に長期的に活躍してもらうには、本人の意向を尊重したキャリア支援が重要です。事業者は、従事する業務内容や注意点を丁寧に説明し、本人の希望や目標を確認しなければなりません。
その上で、将来のキャリアパスを本人と共同で設計し、「キャリアアップ計画」を作成します。この計画には、介護福祉士などの資格取得支援や日本語能力の向上に向けた具体的なサポート内容を盛り込むことが求められます。
ハラスメント対策の実施
利用者の自宅で起こりうるハラスメントから、外国人材を保護するための体制作りが義務付けられています。具体的には、ハラスメントを未然に防ぐための対応マニュアルを整備し、職員全員で共有することが必要です。
また、万が一問題が発生した際に、外国人材が母国語でも相談できる窓口を設置し、誰でも分かるように徹底しなければなりません。利用者やその家族に対しても事業所の方針を明確に伝え、安心して働ける環境を確保する責務があります。
現場で不測の事態に備えたICTの活用を含めた環境整備
一人で業務を行う訪問介護では、不測の事態への備えが重要です。事業者は、緊急時の連絡フローを定めたマニュアルを整備し、必要に応じて他の職員が迅速に駆けつけられる体制を構築する必要があります。
また、スマートフォンやタブレットなどのICT機器を活用し、サービス記録の共有や事業所とのコミュニケーションを取る環境を整備することも求められます。その結果、業務の安全性と効率性を両立させることも可能です。
受入れ事業所に求められる対応
サービスの質を担保し、利用者の理解を得るために、事業者が行うべき2つの対応が定められています。
- 外国人介護人材の実務経験等
- 利用者・家族への説明
外国人介護人材の実務経験等
訪問介護に従事する外国人材には、原則として介護施設などで1年以上の実務経験が求められます。理由としては、さまざまな状況判断が求められる訪問介護の現場で対応できる、基礎的なスキルと経験を持っていることを確認するためです。
ただし、実務経験が1年に満たない場合でも、日本語能力試験(JLPT)N2以上に合格しているなど、高い日本語能力を有している場合は、例外的に従事が認められることがあります。
利用者・家族への説明
外国人材が訪問サービスを提供する場合、事業者は事前に利用者とその家族へ丁寧な説明を行い、書面で同意を得なけらばなりません。説明すべき内容には、次のようなものがあります。
- 外国人材が訪問する可能性があること
- 外国人材に実務経験があるかどうか
- 業務中に見守りカメラなどのICT機器を使用する可能性があること
- 不安な点があった際の事業所の連絡先など
透明性を確保し、信頼関係を築くための重要な手続きです。
受入れ事業所に求められる配慮
受け入れ事業所には、より良いサービス提供と外国人材の定着を促すために、状況に応じた柔軟な配慮が求められます。
- 訪問先の選定への配慮等の実施
- 外国人介護人材の状況に応じたOJT等への配慮の実施
訪問先の選定への配慮等の実施
外国人材をどの利用者の担当にするかは、機械的に割り振るのではなく、双方の状況を総合的に考慮して慎重に判断することが求められます。具体的には、利用者の心身の状態、認知症の程度、住環境、利用者本人や家族の意向を十分に検討する必要があります。
同時に、外国人材本人の介護技術の習熟度や日本語でのコミュニケーション能力、本人の希望も考慮し、ミスマッチが起こらないよう配慮することが重要です。
外国人介護人材の状況に応じたOJT等への配慮の実施
OJTは、全ての外国人材に統一的なプログラムを実施するのではなく、一人ひとりの状況に合わせて内容を調整することが望ましいとされています。たとえば、介護経験が浅い人材や日本語に不安がある人材に対しては、同行訪問の期間を通常より長く設定することが考えられます。
また、定期的な面談の機会を増やして不安を解消したり、個別の日本語学習支援を手厚く行ったりするなど、成長ペースに合わせたサポートが定着につなげられるポイントです。
適切な制度運用と国による支援
制度が正しく運用されるよう、国は事業者の監督を行うと同時に、受け入れを後押しするための支援策を講じています。
- 適切な制度運用に向けた取り組み
- 国による支援
適切な制度運用に向けた取り組み
制度が形骸化しないよう、国が委託する巡回訪問等実施機関が、事業所の遵守事項の履行状況を定期的に確認します。確認を通じて、ルールの不遵守や不適切な運用が認められた場合、改善に向けた指導が行われます。
それでも改善が見られない悪質なケースでは、外国人材の受け入れ停止や事業所名の公表など厳しい措置が取られるので注意しましょう。
国による支援
国は、事業者が外国人材をスムーズに受け入れられるよう、様々な支援策を用意しています。事業者の負担を軽減し、制度の定着を後押しするためのサポートは次のとおりです。
- 外国人材が母国語で安心して悩みを相談できる窓口を強化・周知する
- 日本語学習や介護福祉士などの資格取得を後押しし、キャリア形成をサポートする
- 小規模な事業所でも研修やICT導入などの環境を整えるための助成金を支援する
- 優良な受入れ事例などを広く共有して、全体のレベルアップを図る
- 訪問入浴介護など、特別な技術が必要なサービスの研修体制の構築を支援する
- 技能実習生の受け入れに関する「事業所開設後3年」の要件を、法人の設立年数やサポート体制が整っている場合に緩和し、新規参入しやすくする
このように、訪問介護の分野で外国人材が活躍できるようになる一方で、受入れ事業所には研修やOJT、利用者への説明、国のガイドライン遵守など多くの対応が求められています。
しかし、すべての準備や制度対応を自社だけで行うのは簡単ではありません。そのような場合は、外国人材採用支援の専門サービスを活用することで、制度理解から採用・定着まで総合的にサポートを受けられます。
次の章では、介護人材のサポートに強みを持っている「外国人材採用ラボ」について詳しく紹介します。
介護人材でお悩みなら「外国人材採用ラボ」をご活用ください
外国人材の訪問介護が解禁されたものの、受け入れ準備や複雑な運用ルールへの対応は、事業所にとって大きな負担となります。人材探しから採用後の法定支援まで、何から手をつければ良いか分からないというお悩みも多いのではないでしょうか?
そうした課題を解決し、スムーズな外国人材の受け入れを実現するのが「外国人材採用ラボ」です。最後に、外国人材採用ラボの概要と、サービスの詳細を紹介します。
外国人材採用ラボとは
「外国人材採用ラボ」とは、株式会社クレイプラスが運営する外国人材紹介サービスです。企業の社風やビジョンに合った人材との出会いを実現し、高い定着率につなげています。外国人材採用ラボの主な強みは次の3点です。
- 豊富な実績:中小企業の人手不足に長年向き合ってきた経験がある
- マーケティング力:国内外から幅広く優秀な人材情報を収集できる
- 丁寧な面談:ミスマッチを防ぎ、高い定着率を実現できる
目先の労働力確保だけでなく、企業の持続的な成長まで見据えたサポートを提供してくれる、信頼できるパートナーといえるでしょう。
外国人材の紹介サービス
「外国人材採用ラボ」では、特定技能制度の要件をクリアした、即戦力となる優秀な人材をご紹介しています。企業の採用活動を効率化し、質の高い人材確保を実現するサービスには、次のような特徴があります。
- 確かなスキルと日本語力を持つ即戦力を紹介できる:紹介する人材は、介護技能評価試験と日本語能力試験の両方に合格済みで、入社後すぐに現場で活躍できるスキルが保証されている。
- 採用活動をワンストップで支援する:候補者の選定から面接設定、採用決定までを一貫してサポートし、企業の採用活動にかかる時間と労力を大幅に削減する。
- 介護分野の細かなニーズに対応する:人手不足が深刻な介護分野の細かなニーズにも柔軟に対応し、企業に最適な人材とのマッチングを実現する。
企業の採用活動の負担を減らし、自社に合った優秀な人材をすぐにでも確保したい企業にとって、心強いサービスといえるでしょう。
義務的支援代行サービス
特定技能1号の外国人材を採用した企業は、法律で定められた10項目の「義務的支援」を行わなければなりません。専門知識と多くの工数を必要とする義務的支援ですが、「外国人材採用ラボ」の代行サービスを利用すれば、負担を大幅に軽減できます。主な支援内容は次のとおりです。
- 生活全般のサポートをする:住居の確保、銀行口座の開設、携帯電話の契約などを支援してくれる。
- 各種手続きへ同行する:役所での住民登録や社会保障に関する手続きなどに同行し、サポートする。
- 定期的な面談を実施する:3ヶ月に一度の定期面談を実施し、仕事や生活上の悩みを聞き取り、孤立を防ぐ。
- その他のサポートを実施する:日本語学習の機会提供や、地域住民との交流促進なども支援する。
専門知識が必要な難しい手続きや業務を一任できるので、企業の担当者は本来の業務に集中できます。法令を遵守しながら、外国人材が安心して働けるサポート体制を整えたい場合に最適なサービスです。
まとめ
訪問介護で外国人材の受け入れが解禁された背景と、受け入れ事業者に求められる研修や運用ルールなどの改正内容について解説しました。介護の人材不足が深刻化するなか、日本の訪問介護現場を支える担い手として、外国人材への期待が高まっています。
しかし、受け入れ事業者には、質の高いケアを提供するための研修やOJT、ハラスメント対策、利用者への説明など、多岐にわたる義務と配慮が求められています。これら複雑な制度への対応や、法律で定められた支援体制の構築をすべて自社だけで行うのは、決して簡単ではありません。
そのような場合に頼りになるのが、採用から定着までをトータルでサポートする「外国人材採用ラボ」です。人材紹介から法律で定められた義務的支援の代行までをワンストップで対応してくれるため、法令を遵守しながら安心して外国人介護人材を受け入れられます。
訪問介護分野における人材確保と質の高いサービス提供を目指す経営者・人事担当者の方は、「外国人材採用ラボ」の活用をご検討ください。少しでもご興味をお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください。


 オンライン開催
オンライン開催